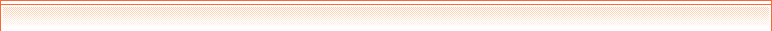|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
2月22日にミュージアム・カフェ会、無事に終了いたしました。遅ればせながらですが、その様子をご報告します。 当日は、もともと天文や旧暦に興味をお持ちだった方から、国立科学博物館の深海展でダイオウイカを見て以来 科学イベントに興味を持ったという方(なんと!)まで、幅広くご参加いただきました。ありがとうございました。 ゲストにお招きした西城 惠一さんは、素敵な笑顔がチャームポイント。 普段は、国立科学博物館の理工学研究部にて、主に江戸時代の天文学について研究されています。 西城さんとのおしゃべりのお供に、形のかわいらしい金平糖と、それにあう日本茶もご用意しました♪ --------------------------------------------- さて、今回のテーマは『カレンダーの作り方』。 1日の長さを知るための時計?
棒を立てて、できた影の長さを毎日測っていくと、その影の長さが1番長くなるのが冬至の日。冬至の日から次の冬至の日までが1年になる、とのことでした。 ここで、「江戸時代に、影を測るのに精度のよい定規とかあったんですか?」 ありました!
----------------------------------------------------------------------------- さて、後半は、江戸時代の天文学者の話題へ。 日本のカレンダーは、平安時代におとなりの中国から導入されたものが、江戸時代になるまでそのまま使い続けられていて、 渋川晴海はそのズレに気付いて、改暦を行ったのだそうです! 改暦にあたって、当時、より精度の高かった中国のカレンダーについて調べただけでなく、 江戸時代の技術の高さと、 --------------------------------------------- 参加者のみなさんとのおしゃべりも盛り上がりを見せ、カフェ会が終わった後まで続いたほどでした。 さて、今回のカフェの内容に関する展示は、国立科学博物館にてご覧いただけます♪
PR
|
 |
 |
|
忍者ブログ [PR] |