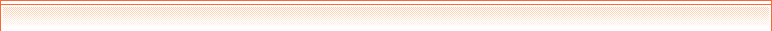|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
2月22日にミュージアム・カフェ会、無事に終了いたしました。遅ればせながらですが、その様子をご報告します。 当日は、もともと天文や旧暦に興味をお持ちだった方から、国立科学博物館の深海展でダイオウイカを見て以来 科学イベントに興味を持ったという方(なんと!)まで、幅広くご参加いただきました。ありがとうございました。 ゲストにお招きした西城 惠一さんは、素敵な笑顔がチャームポイント。 普段は、国立科学博物館の理工学研究部にて、主に江戸時代の天文学について研究されています。 西城さんとのおしゃべりのお供に、形のかわいらしい金平糖と、それにあう日本茶もご用意しました♪ --------------------------------------------- さて、今回のテーマは『カレンダーの作り方』。 1日の長さを知るための時計?
棒を立てて、できた影の長さを毎日測っていくと、その影の長さが1番長くなるのが冬至の日。冬至の日から次の冬至の日までが1年になる、とのことでした。 ここで、「江戸時代に、影を測るのに精度のよい定規とかあったんですか?」 ありました!
----------------------------------------------------------------------------- さて、後半は、江戸時代の天文学者の話題へ。 日本のカレンダーは、平安時代におとなりの中国から導入されたものが、江戸時代になるまでそのまま使い続けられていて、 渋川晴海はそのズレに気付いて、改暦を行ったのだそうです! 改暦にあたって、当時、より精度の高かった中国のカレンダーについて調べただけでなく、 江戸時代の技術の高さと、 --------------------------------------------- 参加者のみなさんとのおしゃべりも盛り上がりを見せ、カフェ会が終わった後まで続いたほどでした。 さて、今回のカフェの内容に関する展示は、国立科学博物館にてご覧いただけます♪
PR
|
 |
 |
|
ミュージアムカフェ会 「カレンダーの作り方~星をみつめた江戸の人たち~」 は、本日予定通り開催いたします。 皆さまにお目にかかれることを楽しみにしております! 2月22日(土)、東京・上野の国立科学博物館で「ミュージアム・カフェ会 」を開催します。 テーマは 「カレンダーの作り方」 ・・・しかも、『江戸時代』にタイムスリップします! 江戸の人たちは、カレンダーを作るために星をみつめていた!? 当時のカレンダーってどんなもの? どうやって暦を作っていたの? 300年前 の日本人はどうやって星空を観察していたのだろう? ミュージアムで研究者と一緒にお茶会 しよう♪ 江戸の人たちにも親しまれていた、 ミュージアム・カフェ会 「カレンダーの作り方~星をみつめた江戸の人たち~」 【 日時 】 2014年2月22日(土)14:00~15:30 (開場13:30) 【 ゲスト 】 西城惠一さん(国立科学博物館理工学研究部) ひとこと: ふだんは天体観望会を開催していますが、江戸時代気分でこんぺいとうを楽しみながらお茶会するのは初めてなのでちょっとドキドキしています。皆さまのご参加をお待ちしています。 【ファシリテータ】 中山由紀子(国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ) ひとこと: 毎日私たちも使っているカレンダーが、江戸時代には一体どんなものだったのか、気になります!江戸の人たちが星を観察していたなんて、なんだかステキ ー!(わくわく) 【 対 象 】 中学生以上ならどなたでもご参加いただけます 【 定 員 】 20 名(メールによる事前申込制・先着順) 【 会 場 】 国立科学博物館(東京・上野公園) 地球館 3階 講義室 アクセス http://www.kahaku.go.jp/userguide/access/ フロアマップ http://www.kahaku.go.jp/userguide/access/floormap/ 【アクセス】 JR「上野」駅(公園口)から徒歩5分 【参加費】 200 円(日本茶&こんぺいとう付き) + 別途入館料が必要になります 【申込方法】 参加ご希望の方は、お申込みフォームで必要事項をご記入ください。 https://ssl.form-mailer.jp/fms/34ec0117281590 ※本イベントは2013年12月22日に国立科学博物館で開催されたイベント「星が導く暦」と同様の内容 ですのでご了承ください。 ※当日は、記録・広報のために写真等の撮影をいたします。また、お写真やご発言内容をレポートとしてWEB等へ掲載させていただく場合があります。 ※お申込み後、数時間経過しても返信が無い場合には、メールアドレスの記載間違いの可能性もあります。お手数ですが、メールアドレスをご確認のうえ、再度お申込ください。 ※頂いた個人情報は本イベントのご案内にのみ使用いたします。 【 主 催 】 科博SCA(国立科学博物館サイエンスコミュニケータアソシエーション) サイエンスカフェ分科会 【 共 催 】 独立行政法人 国立科学博物館 【 協 力 】 ウィークエンド・カフェ・デ・サイエンス(WEcafe) 事務局 ポスターのダウンロードはこちら (クリックして拡大できます) |
 |
 |
|
国立科学博物館サイエンスコミュニケータ・アソシエーション(科博SCA)サイエンスカフェ分科会は、国立科学博物館サイエンスコミュニケータ養成実践講座の修了生有志によるボランティア団体です。 サイエンスカフェ分科会の運営する各種SNSをご案内します。 「サイエンスカフェ分科会」 Twitter @SCAcafe (2015年~) https://twitter.com/SCAcafe 「ミュージアム・カフェ会」 Facebookページ「ミュージアム・カフェ」 (2014年~) http://www.facebook.com/museumcafebysca Twitter @edohoshi_koyomi (2013年~) http://twitter.com/edohoshi_koyomi |
 |
 |
|
2月22日(土)、東京・上野の国立科学博物館で「ミュージアム・カフェ会 」を開催します。 テーマは 「カレンダーの作り方」 ・・・しかも、『江戸時代』にタイムスリップします! 江戸の人たちは、カレンダーを作るために星をみつめていた!? 当時のカレンダーってどんなもの? どうやって暦を作っていたの? 300年前 の日本人はどうやって星空を観察していたのだろう? ミュージアムで研究者と一緒にお茶会 しよう♪ 江戸の人たちにも親しまれていた、 ミュージアム・カフェ会 「カレンダーの作り方~星をみつめた江戸の人たち~」 【 日時 】 2014年2月22日(土)14:00~15:30 (開場13:30) 【 ゲスト 】 西城惠一さん(国立科学博物館理工学研究部) ひとこと: ふだんは天体観望会を開催していますが、江戸時代気分でこんぺいとうを楽しみながらお茶会するのは初めてなのでちょっとドキドキしています。皆さまのご参加をお待ちしています。 【ファシリテータ】 中山由紀子(国立科学博物館認定サイエンスコミュニケータ) ひとこと: 毎日私たちも使っているカレンダーが、江戸時代には一体どんなものだったのか、気になります!江戸の人たちが星を観察していたなんて、なんだかステキ ー!(わくわく) 【 対 象 】 中学生以上ならどなたでもご参加いただけます 【 定 員 】 20 名(メールによる事前申込制・先着順) 【 会 場 】 国立科学博物館(東京・上野公園) 地球館 3階 講義室 アクセス http://www.kahaku.go.jp/userguide/access/ フロアマップ http://www.kahaku.go.jp/userguide/access/floormap/ 【アクセス】 JR「上野」駅(公園口)から徒歩5分 【参加費】 200 円(日本茶&こんぺいとう付き) + 別途入館料が必要になります 【申込方法】 参加ご希望の方は、お申込みフォームで必要事項をご記入ください。 https://ssl.form-mailer.jp/fms/34ec0117281590 ※本イベントは2013年12月22日に国立科学博物館で開催されたイベント「星が導く暦」と同様の内容 ですのでご了承ください。 ※当日は、記録・広報のために写真等の撮影をいたします。また、お写真やご発言内容をレポートとしてWEB等へ掲載させていただく場合があります。 ※お申込み後、数時間経過しても返信が無い場合には、メールアドレスの記載間違いの可能性もあります。お手数ですが、メールアドレスをご確認のうえ、再度お申込ください。 ※頂いた個人情報は本イベントのご案内にのみ使用いたします。 【 主 催 】 科博SCA(国立科学博物館サイエンスコミュニケータアソシエーション) サイエンスカフェ分科会 【 共 催 】 独立行政法人 国立科学博物館 【 協 力 】 ウィークエンド・カフェ・デ・サイエンス(WEcafe) 事務局 ポスターのダウンロードはこちら (クリックして拡大できます) |
 |
 |
|
忍者ブログ [PR] |